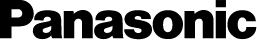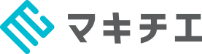― お知らせ ―
令和7年(2025年)日本補聴器工業会 年頭所感
超高齢社会において「きこえのケア」は最重要課題
一般社団法人 日本補聴器工業会
理事長 東條大輔
皆様、新年あけましておめでとうございます。令和7年を無事に迎えられたことを謹んでお喜び申し上げるとともに、平素私ども日本補聴器工業会に対してあたたかいご理解とご支援を頂戴している皆様に、心よりお礼を申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの感染は一定の落ち着きを見せましたが、年初から能登半島地震や豪雨、記録的な猛暑などがありました。被災されました方々には心よりお見舞い申し上げます。また世界に目を向けると各地で戦火が続いております。新しい年は平和で穏やかな年に向かうことを切に希望致します。
さて、昨年の当工業会会員各社の補聴器出荷台数は、11月までの累計で前年比98%であります。これは猛暑や災害などの社会的な環境がマイナス要因となったことが考えられますが、9月以降は前年比プラスで推移しており、2024年年間としては過去最多であった2023年65.2万台前後と予想されます。
昨今、新聞、テレビ、チラシ、インターネットなど様々なメディアによる情報発信を通じて、きこえに関する関心度は徐々にではありますが高まってきていると感じます。しかしながらこれらは、補聴器以外のアイテム(集音器等)がその多くを担っていることも否めません。そのようななかで補聴器に関する正確な情報を発信、周知していくことが重要です。当会と致しましてもホームページの充実を図るなど、わかりやすい情報の周知・啓発を進めて参ります。
2019年に「Japan Hearing Vision」がまとめられ、①補聴器購入費助成制度、②補聴器認定技能者の公的資格化、③補聴器認定技能者の店舗在籍義務化が課題として組み込まれました。補聴器業界としてこれらの課題の実現に向けた取組みを強化・推進する必要があります。
2025年日本補聴器工業会としては、難聴者及び補聴器に関する大規模調査である「Japan Trak 2025」の実施、「補聴器販売店舗数調査」など、補聴器に関する実態を把握する活動を行います。また「難聴のケアがされていないことによる経済的損失」に関連する各国分析結果を考察するなど、わが国の補聴器業界の現在の立ち位置を改めて確認し、推進すべき課題についての具体的な施策へ繋げていきたいと考えます。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会においては、昨年より「ACジャパン 難聴啓発キャンペーン」や「聴こえ8030運動」の提唱など、聴覚ケアの啓発を積極的に展開されています。聞こえの不自由さを感じた方へ早期の聴力検査を促し、その適切な難聴診断結果に基づいた補聴器装用ルートとして、補聴器相談医から認定補聴器専門店・認定補聴器技能者への連携を強化する取り組みも進められております。
全国各地の自治体においては補聴器購入費助成制度が拡大しています。このような制度が拡大していくなかで、難聴者の誰もが適切なルートで同じく助成を受けることができるよう、国の参画及び必要な法整備について早期実現を強く求めて参ります。
本年は、団塊の世代と言われる人口の多い世代が75歳以上となります。わが国は、高齢者人口が2040年まで増加し、超高齢社会が続いていくことが予測されています。その為、難聴者や聞こえにくさを感じられる方々が今後益々増加していくこととなりますので、高齢難聴者がいきいきと活動できる社会の構築が求められます。
日本補聴器工業会の役割は、難聴の方々がより良い生活を送れるよう、補聴器に関する技術課題の解決とともに、その適正な供給に努めることであります。超高齢社会が進展するなかで「きこえのケア」はわが国にとって最重要課題のひとつであり、現在、難聴対策や補聴器の適切な普及に向けた仕組み作りにおいて、将来に向けて重要なターニングポイントを迎えています。医学会、補聴器関係団体、難聴者関係団体等との連携を密に図り「きこえのケア」推進に努力して参りますので、本年もより一層のご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、新しい年が皆様にとって健康で充実した年となりますよう祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせて頂きます。